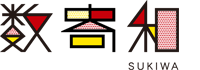ゲスト:吉田加南子(詩人・フランス文学者)
皆様、お暑い中ありがとうございます。椅子が少ししかないので、ちょっと体調悪い方には譲り合って頂ければ。離れていると、後ろの車の音で聞きにくいので、前によっていただければ。前にお願いいたします。
岸田憲和:沢山集まっていただいて、正直ホッとしています。暑いので、今日はどれ位人に集まっていただけるか1時間前は心配していたんですけど。元々、私は織もの会社に勤めていて、30年前転勤で東京に来て、その2年後位に確か大手町画廊というところで斉藤さんの絵を初めて拝見して、それからのご縁なんですけど、織物会社を20年前に辞めて、日本画を制作される時に使用される紙とか絵絹、また絹織物、日本画の方々が制作された作品を掛軸に仕立てたり、額装をしたり、また時には古いものを修理すること等を生業としております。私は、数寄和の代表の岸田です。会社を設立して、今から丁度12年前に私の実家がある滋賀の大津に2階建ての小さなギャラリーを設立して、翌年に西荻にこのスペースを始めました。数寄和大津を建てた記念すべき第一回の展覧会を斉藤先生にやっていただきました。その後、何回か展覧会をしていただいております。
本日は吉田加南子さんをお迎えして、斉藤典彦さんの作品の魅力を皆さんとお話を伺いながら、じっくりもう一度味わいたいと思います。それでは、ご紹介します。ゲストの吉田加南子さんです。現在、学習院大学でフランス文学を教えていらっしゃいます。それでは、1時間位ですが、皆さんとゆっくり楽しみたいと思います。宜しくお願いいたします。
吉田加南子(以下、吉田):わたしからか、斉藤先生から口を切られますか?
斉藤典彦(以下、斉藤):この前、簡単に打合せを行ったのですが、なぜ絵を描き始めたのかとか伺ってみたいと言っておられたので、その辺りから話し始めましょうか。
吉田:斉藤先生が話を始めなくても、もうわたしたちは会場に入って、実はある世界にいるわけで、斉藤先生の作品に包まれています。お作を目の前にして、言葉でどれほどのことを語りうるのか、果たして何を言うことができるのか、心もとないのですが、打合せで斉藤先生とお話をして、とても幸福になりました。
わたしのごく簡単な感想を申し上げますと、「自然」ですよね。自然がとても柔らかにわたしたちを包んでくれていて、その自然と人間との関係というのでしょうか。
わたしは詩を書いておりますので、詩の方のことで言うと、「詩」というのは詩と詩の外にあるもの、詩ではないもの―詩の外にあるものというのは、各人間自身も含めて、人間も自然もあるいは社会的なことも、あるいは歴史的な時間もすべて含めて、「詩」が詩の外にあるものといかに向き合っているか、いかに対峙しているか、あるいはそれをどう受けとめているかということが、詩の力になるのだと思います。少し図式的かもしれませんが、絵の魅力というのは、絵が絵としてあるのだけど、実は絵ではない、ものっていうか、実際の自然とか人間とか、あるいはそこで生きてきた人間の息遣いとかそういうものを受容しつつ、表現しているかで、絵が立ち上がるのではないのでないかと大ざっぱに考えております。作品と作家は、作品と作品の外にあるものと、場合によっては戦い、場合によってはせめぎ合いをしたりするわけですが、斉藤先生の作品は会場にあるのを拝見しますと、作品がある以上、戦いがまったくないとはいいきれないかもしないけれども、しかし、そこにすごく柔らかな空間とか時間とか、あるいは子どもが遊びあっているような、戯れているようなふうに見えます。それがあるので、作品自体、作品の中にある樹とか空気、今回の題でいう森とか声が聞こえてくるように感じます。そういったことが斉藤先生の絵の魅力ですが、実はずっと以前から作品を拝見していたわけでなく、数寄和さんとのご縁で拝見したのが初めてで、最近からです。
今のような作品を描くに至るまでについては、図録でしか知りませんが、鳥の絵や十字架など、あるいは板を使ったり、イギリスに留学なさったりしていろいろな経験を経て、今の作品があるのだと思いますが、そういう作品創造に関わる影響と言うか、どういうものを見たり聞いたり、あるいは働きかけられたりしたのかまた、子供時代に初めから日本画の絵描きさんになろうとしたと伺っておりますが、そういうこととか、イギリスにも留学されて、作風も変わり、支持体もいろいろ変えていらっしゃるので、その折々にどういうものが好きだったか、どういう絵を見ていたか等を緩やかにざっくばらんに伺いたいと思います。
斉藤:私の作品を、戦わないという表現をされて…
吉田:それは見た人間がそう思っただけですよ。
斉藤:非常に有難く思います。とても適切な批評をいただいて、そう思わざるを得ないのですが、子どもの頃から絵は好きでしたね。
吉田:その絵っていうのは、身近にお家の中に沢山ある環境だったのかあるいは画集で見たりなさったのか?また、その絵というのはいわゆる世界名画みたいなものだったのか身近に絵描きさんがいて、それを見ていたのかとか?
斉藤:絵は現物を見ていたというわけではなく、どちらかと言うと美術全集的なもので見ていた。何か、ちょこちょこ変な人が出てくる変な家系だった
吉田:それはどういう意味ですか?
斉藤:3代おきに身上をつぶすような人が出てきたりとか。
吉田:道楽者という意味ですか?
斉藤:そうですね。
吉田:商売をされている家系だったんですか?商売をしようとして潰している家系もあるし、本当に道楽をして潰している家系もあるし。
斉藤:江戸の終わりから明治になる頃、曾祖父位の人にも大正舎麗山たいしょうしゃれいざんという質商だったと思うんですけど、商売をやりながら文学に親しむような、そういう傾向の人がいて。
吉田:芸事が好きで。自分がやる方じゃなくて見る方ですか
斉藤:芸事が好きで、自分も好きでやっていて。自分も俳句を詠んでいたんですよね。
吉田:自分がやるっていうと、義太夫ですね。
斉藤:あっ、文楽ではなくて、文学(ぶんがく)です。
吉田:あっ、ごめんなさい。文楽ぶんらくって聞こえて。道楽者というとそっちの方だと思って。文学ですね、失礼いたしました。
斉藤:今も、菩提寺にうちの街の唯一の句碑があって、それに俳句が書かれていて。どっかで聞いたこともあるような気がしているのですが…
吉田:俳人?
斉藤:俳句をちょっと書いていたんですよね。「すそはまだくらきにあけてゆきのみね」という。
吉田:それは初めて聞きましたね。
斉藤:自分が検索しても引っかからなかったのでオリジナルかなとも思うんですが。
吉田:先生から曾祖父とおっしゃられると、明治の始めから江戸末期ですか
斉藤:そうですね、曽祖父よりもうちょっと上かもしれませんね。文久頃から明治初期と、幕末と時期がちょっと被っている かもしれませんが
それから、何代か経って実際の祖父は書家をしていた。
吉田:書家として暮らしていた
斉藤:書家として暮らしていました。だから、近所には祖父の開いていた習字の塾に来ていた方がご存命でいらっしゃいますが。
吉田:おじい様が書を教えたり書いたりとかするのを、実際にご覧になられていたのですか?
斉藤:僕が生まれる前に亡くなっているので、実際は見ていないんですけど、家の大きな部屋の床の間に掛軸が掛っているのを見ていたので。家に画集があったというのも、母親が美術をやりたかったが、戦後のバタバタで諦めたという人だったので。
吉田:美術学校に通ったけど、そちらには進まれなかったという
斉藤:いや、そこに行くまでではなかったんですけど、地元の絵描きさんについて、油絵を習っていたりしたんですけど、諦めて高校出て就職したという。
吉田:そうすると、画集はやっぱり身近にあったわけですね。
斉藤:そうですね。中学生の頃からいわゆる印象派だけではなくて、たまたまあった浮世絵とか日本の作品が描いていたりする画集を身近で見ていて。日向ぼっこしながら、縁側でゴロゴロしつつ、その辺で見ていて。
吉田:小学生とか中学生くらいの時に?
斉藤:そうですね。だからもうその頃から、会社に入って、サラリーマンとかには向いてないな。絶対に研究者とか独りでやる仕事でないと駄目だなと。
吉田:もうその頃に、何となく思っていらしたんですね。
斉藤:そうですね。
吉田:岸田さんからのお話では、図鑑とかがお好きだったと伺っておりますが…。
斉藤:図鑑とかも好きでしたけどね。そういう画集があったり、図鑑とか、民族学的なものへの興味が今の原点で今に至る所だと思う。今回の展覧会にすごく影響していると思うのが、岸田劉生の『美乃本體』という本が今日はお借りして丁度持ってきた母の本で、これが初めて読んだ美術の本だった。
吉田:芸大に入る前ですか?
斉藤:高校生位ですかね。旧仮名遣いで読みにくかったのですが岸田劉生と言いますと麗子像とかの絵などを追及したような人だったが、特に麗子像や晩年になって描いた日本画なども好きですが、最終的には初期の浮世絵のでろりとした美しさに惹かれていって。そういったものが写実を通り越したものに在るかもしれなくて。そういったものに惹かれていたのは青年期独特のちょっと暗いものが好きみたいな、若気の至りがあったんですけどね。
吉田:若気の至りというか、ちょっと不可解なものに惹かれるということなんでしょうね。
斉藤:ええ、崩れるものとか崩れかけるものに惹かれる。人それぞれかもしれないけど、若い時は結構、暗い絵を描くことが多いと思うんですね。わざと暗くしたりとか。そういうようなものに興味があったんですよね。
吉田:「でろりとした」って面白いですね。崩れていて暗くて、でろりとしているって。
斉藤:ちょっと肉感的な感じでね。村上華岳の初期の作品に典型的に見られる、最終的に宗教的になっても華岳が持っていたものかもしれないんですが、そういったものに惹かれるような所が何処か共通していて。
徳岡神泉もそうですが、最初はバリバリ写実をやっていたのですが、最後は割と象徴的な画面になっていった。この辺が高校生時代や学部の頃の僕のお手本みたいなところがあったので、大学時代には、芸大的な絵とはあまり馴染めなかった。
吉田:実は、わたしは絵は専門外で素人の人間なので、わたしより聞いてくださっている皆さんの方がよくお分かりになられると思うのですが。
斉藤:東京芸大の造形的に絵を作っている感じとは違って…
吉田:それは、初めから変わっていたけれども、感覚的なものがちょっと方向が違ってというようなことですか?
斉藤:芸大時代同世代には、現役が2人いたんですけど、すごい年齢的にはバラバラで。上は4浪から5浪が当たり前という変な学年でした。
吉田:先生は、簡単に現役でお入りになったと伺っています。
斉藤:現役で入ったんですけど、予備校もあまり行かずに入ってしまったので、美術業界の人しか分からないんですけど、僕だけ国産三菱のuniという普通の鉛筆を使っていて、皆周りは外国のSTAEDTLERを使っていて。鉛筆デッサンを描く時も、僕だけ赤黒い汚い色調で、周りはブルーがかった綺麗な色調で、全く違っていて浮いていましたね。
吉田:そのための受験勉強もされなくて?
斉藤:僕はやることはやったんですよ。でも、たまたま入って。
吉田:運も実力の内ですよ。
斉藤:そう言ってもらえると本当に良かったなと。でも、変わっていたクラスで本当に変わっていた学年でした。今でこそ先生達も大学出の先生ばかりですが、当時は塾育ちの先生もいらっしゃいましたし、高等小学校とかしか出ていないような先生もいましたね。そうすると絵に対する価値観もいろいろ有ったので、そういういろいろな先生の価値観に出会えたことが良かった。
吉田:入学されたのは何年ですか?
斉藤:51年。
吉田:先生、それはまだお生まれになっていませんよ。
斉藤:昭和51年ですね。
吉田:昭和51年ということは、1976年。
斉藤:僕らが博士を出るころになったら、先生らも美術学校か大学出の先生になっていました。
吉田:そういう時代だったんですね。わたしのフランス留学が1976年からで4年行ったんですが、帰ってきたら日本が変わっていた。フランスから帰ってきて、逆カルチャーショックもあったのですが、留学前には学生がお店には行かなかったのに、4年後に戻ってきた時には学生が「どこどこのお店とかに行って―」とか言っていて、雑誌では『ポパイ』とか『ターザン』が出てきていて、ある意味消費的な豊かさがある時代になって、しばらくカルチャーショックでした。ある意味では、先生たちも変ったんじゃないでしょうか。世代的に交代する時期だったとも思うのですが。
斉藤:時代的にいうと、高度成長期からバブルに変わる頃に学生時代を過ごしたので、今思えばとんでもない日々だったと思うんですが。僕らみたいな変な絵も非常に買って頂けて、今と違ってやりたいことがやれた。それにお金の方も心配することなく出来たという良い時代でした。本当に今と、今の学生と違って。
吉田:今は違いますよね。
斉藤:日本画の中でも、様々なちょっと変った表現が出てきて、同い年で1学年下の河嶋淳司君というのが1984年に初めて日本画作家で、その後ワタリウムになっているワタリで個展をしたり。
吉田:ワタリウムになる前のワタリ?
斉藤:ギャラリー・ワタリという所でした。ちょっと今とある場所が違うと思うんですけど、道の反対側にあってね。そこで個展をやって、美手帖(美術手帖)なんかに出て。そういった、公募展に出さなくても個展でやっていきたい作家希望者が、自分の作品を打出せる受け皿があって。その後に、岡村桂三郎君、千住博君、マコトフジムラ君とかが出てくるような時代だったので、そんな同年代や後輩がガンガン活躍しはじめて、自分も何とかしなきゃいけないと非常に悩んだ時期でもありました。
吉田:やっぱり、ライバル意識も有ったんですか?
斉藤:ライバル意識というか、学年は一応先輩だったけど、下の学年や若い子がどんどん活躍していると、これで良いのかとか思ったりしてね。そういう中で作風を工夫して板に描いたような作品を山種に出して、賞を頂いたんですね。それで多少、自分らしい作品を少し作れるようになったのかなと思えました。
吉田:それは、対社会、社会に対して、積極的にご自分を打出せたということですか?そういうようなニュアンスでしょうか?
斉藤:そうですね、そういうようなことが少し出来たかなと。ただ、そこで日本画に対しても、好きだけど嫌いみたいなアンビヴァレントな部分があって、日本画を何とか変えれないかという気持ちが有ったりして。
吉田:その好きだけど嫌いというのは、具体的にはどういう部分ですか村上華岳とか浮世絵の話だとかを聞いて、すごく自然と当然のように日本画を選ばれたように思えるんですが、例えば日本画的な絵の具の感触や技法に自然となじまれて、進まれたのだと思いますが…?
斉藤:そうですね。日本画の絵の具自体は、普通の学生と一緒で、大学に入ってから馴染んでいきました。高校時代は美術部に入っていて、先輩・後輩といろいろと絵とはどういうものかという話をすると自分は日本画的なものが良いんじゃないかという方でした。いわゆる若人の、油絵の方が絶対に良いという人と話すとコテンパンにやられる感じでしたけど、基本的にそういう日本的な傾向の表現が好きで、何処かに持っているという部分が未だに変わらない。ほとんど西洋的な表現になりきれない、なろうと思ってもなれない。
吉田:好きだけど、嫌いと思う時もあったというのは、西洋的な表現の方になろうと思った時もあったという意味ですか?留学されたのはイギリスですよね。そういうことは関係があるのですか?
斉藤:個人的にはそんなに海外なんか行きたくないと思っていました。英語も出来ないし…。
イギリスに行ったのは河嶋淳司君とか岡村君とか新しい絵画表現が出てきて、日本画って何だろう?と非常に盛んに議論されるような時代だったのですけど、そういった時代に留学が出来る機会を頂いて、日本と同じように文明が発達していて、四季があってヨーロッパと同じくらい発達しているような所は何処かという所でイギリスになりました。そして、さっき言った若人的な部分で暗いものに惹かれるという部分を持っていたので。イギリスって、ちょっとひねくれていて暗いというか…
吉田:雨も降って、じとじとしてって言う?
斉藤:例えば、ユーモアもカラッとしてないじゃないですか。
吉田:湿気ですよね。海に囲まれているし。日本も海に囲まれている島だし。わたしがイギリスに行ったのは、留学より前の春休み中の4月で、フランスに行く前に3~4日ロンドンに行ったのですが、雨が降っていて、すごく寂しくて、悲しく暗いロンドンでした。5月、6月は緑豊かで明るいのでしょうけど。
斉藤:イギリスの諺で「4月の雨が5月のバラを呼んでくる」というのがあって、それが良いんですけど、やっぱり湿気がすごいですよね。中国より苔が生えていますよね。
吉田:それは大陸にはないですよね。やっぱり、イギリスですよね。
斉藤:そういう所で出てくる表現は何が同じで、何が違うのだろうというのをその地に住むことで実感してみたいというのも有ったんですよね。さっきお話ししたように、その頃が丁度バブルの名残りだったんで。
吉田:1995,96年?
斉藤:95、96年ですね。加えて言えば、僕らは夏の終わりに行って、冬になって、春・夏の初めに帰ってきたので、どんどん日が短く、暗くなって寒くなっていく時期だったので
吉田:どんどん悲しくなっていきますよね。
斉藤:悲しくなります。漱石がそう言うのも分かるなと言う時期に行ったので。
吉田:でも、その季節にいらしたのは逆によかったんじゃないですか?
斉藤:そうですね。だから、必要以外に絵は描かず、どちらかと言うとこの花が咲く時にはイギリスにはいないんだけどなと思いつつ、ナーサリー種苗店とか園芸店に行って球根や種を買って庭に植えて、今日は芽が出たとかそういうのを楽しみにしていました。
吉田:ガーデニングをされていたのですか?
斉藤:住んでいる場所が庭付きの一軒家の長屋みたいなところだったので。
吉田:場所はどちらですか?
斉藤ロンドンの北の方。
吉田:郊外よりちょっと向こうの方?
斉藤:ここからいうと、国分寺、立川八王子あたりみたいなイメージですかね。中心から40分位地下鉄で行った。だから、ちょっと行けば、畑が広がっていて。
吉田:ああ、イギリスはそうですよね。
斉藤:だから、何をしていたわけじゃないのですが…向こうで実感しました。
吉田:暗いところにいた。湿気があるところで、絵を見て、植物とちょっと触れあいつつ、生活をしていた。
斉藤:そうですね。でも、向こうのいろいろな表現を見ると、自分がこういう育ちをしたから、こういう価値観を持っているから、こういう表現になるというのがすごくストレートなんですよね。海外特有の。美術史がどうのこうのと言うのも無いわけではないのですが、わたしはこうだからこういう風にしか出来ないのよとなっている所がやっぱりあって。
吉田:さっき、ちらっとおっしゃった写実と抽象というのも、何か関係があるんじゃないでしょうか。外側から言うと、これは写実、これは抽象というだけで、思い違いかもしれないけど、作家の方からすると、それがたまたま写実という世界で、というだけなんじゃないでしょうか。もちろん、美術史的な視点も大事だけど、そういう区分ももう関係ないのではと思います。
斉藤:自分がやりたいことをやればいい、やり始めればいいと思った。丁度、その2~3年位前から形が無くなりはじめたんですよね。
吉田:それはイギリスにいらっしゃる前?
斉藤:イギリスに行く2年位前から、自分の中でいろいろ思って。
吉田:それも自然とそうなっていった?
斉藤:そう、でも本当にこれで良いのかとも思ったりする部分もあるわけですが…ただ、向こうの作家の絵とかを見たりして、もうそれでいいんじゃないかと感じて、帰ってきましたが。
吉田:形がなくなっていくことに対して、例えば、何かの出会いや影響等のきっかけがあったりしたのか?それとも、自然と、内発的におのずとそうなっていったのか?
斉藤:板を張る作品で認められたわけですが、それはどんどん過剰になっていくというか、エスカレートしていくわけですよね。そうすると、絵を描くよりも、板を張る作業とか板の存在感自体がどんどん作品の中で大きくなっていく。それはそれでどんどん行けば、何か一つの新しい世界が開けたのかな…とも思わないでもなかったけど、でも、「もう一度描くこととは」に戻った時にそれって必要かなとも思うようになり始めたんですよね。それを取っ払っちゃうと、先ほど言った十字架とかを描いていたのですが、そういったアイコン的な「形を描きたいのか」というと、そういうわけではなくて、その後ろにあるものやそれを浮かび上がらせるイメージみたいなものを形にしたり、表現したいという所があったので、だったらそれだけ描けば良いんじゃないかということになって、形がどんどん無くなっていった。
吉田:余計なものが落ちていったという…
斉藤:削ぎ落とした時に、極端な話、色だけでいいんじゃないか?とかマチエール自体だけでいいんじゃないか?ということを考えたりもした。
吉田:支持体自体も変わったわけでしょう?
斉藤:紙との併用ともいうことが多かったわけですが、最後の方は板だけになっていたり、もう一度紙に戻っていた時期もあった。帰ってきてから初めて本格的に絹に描きだしたんですよね。
吉田:95,96年と伺ったから、もう20年ですね。
斉藤:あっという間でしたけど、
吉田:誰でもあっという間ですけど…。
斉藤:絹を使い始めて今に至るまで良いなと思っている所は、紙だと基本的に絵具が定着するようにドーサがしてあって、紙の上に絵の具の厚みなりが上に積み重なっていくだけなんですよね。表現としてすごく抵抗感は出やすいし、絵画的な空間も視覚的な空間も手前に手前にこっち側に向いてくるんですよね。そういった表現には向いていて作りやすいんですけど、もっと微妙な絵の空間や後ろを含む空間を作りたいと思うと、ちょっとやっぱり難しいわけですよね。それが絹の場合はやりやすい。
吉田:わたしの言葉に置きかえると「巡る」っていうのですが、こっち側だけではない空間の感覚というか、それには時間も関わってきますが、ある種のまた別の動きをもう一つお考えになったのですか?
斉藤:そうですね。直線的に、手前に、手前にではない動きを作っていこうとすると、やっぱり紙だと辛いんですよね。そういう意味でたまたま使い始めたのが絹だった。絹目の間に細かい絵の具や水が染み込んでいったり、極端に言うと裏側にも出ていって、表面上のイリュージョンと違うイリュージョンが後ろ側にもあったり、中間にもあったりとか思うんですよね。引っ込んでは出し、引っ込んでは出して、微妙なところで絵の空間が成り立つ世界を作りたいと思った時に非常に作りやすい。
吉田:打合せの時に「絵の具をさす」という言い方をなさったんですよね。わたしは絵の具は塗るという表現でしか知らなかったので、絵の具をさすという言葉がものすごく魅力的で、いかにも手で仕事をしていて、支持体・絵の具と接していて、それがすごく柔らかなあたり、感触でその作業自体が動いていくという感じがした。多分、聞いている方々には当たり前のことなんでしょうが、わたしにとっては打合せで聞いた言葉の中で、言葉を聞けてよかったなと思いました。
斉藤:今もどうして絹かと言うと、薄い層の重なりが、ある種の絵画そのものと思う気がするんですよね。あそこにぶら下がっている作品も4枚もそういった薄い層が積み重なって出来ているのがある意味では絵そのものだし、ある意味では時間そのものだしという考えがあって。
吉田:それが作品ということですね。
斉藤:それを1枚の画面でやっているということだけなのかなと。刺すという言葉でいうと、水を引いて、繊維の間に色が入っていく。何か、こう…
吉田:浸透していく。やっぱり水分、湿気のある世界でしょうか?
斉藤極端に言うと、刺青を入れているような感じになる時があるんですよね。実際は、刺青を入れたことがないから分からないけど、だからその辺がでろりとした表現との共通ということもあるかもしれません。肌に刺青で絵の具を、模様を彫っていくような同じような感覚に近い世界と言うんですかね。
吉田:会場入口にあるお作品について伺いたいと思っているのですが、4枚重なっていて、今があの季節だから手前に夏を出していて、本来は掛けかえられるようになっているということでしょうか?
斉藤:掛け替えられるようにはなっていますが、掛け替えなくても別に構わないんですけども…
吉田:わたしの発想でちょっと違うことかもしれませんが、季節毎に夏・秋・冬・春と掛けかえていくというと、日本のお家だと襖を簾戸にしたり、季節によって調度の入替えをしますよね。それがまさに空気を巡らせるというか、木のお家だと湿気を吸ったり、入ったりという、木そのもの自体がお家になっても生きているという暮らしの知恵だと思うんですよね。
あの作品を「このままでよい」とおっしゃった通り、このままでも十分何かわかるし、「これが一枚」ともおっしゃったので、うーん…なるほどとも思うのですが、日本の中での住まいということをもしかしたら意識されているのかなと。
つまり、絵をどういう場所に置くのかは、やっぱりとても大きいことですよね。壁面を飾るのか、床の間にお軸を掛けるのかという。支持体や絵具は何か、もちろん水墨画みたいなものもありますし、(ある空間の中に絵を置くということは)絵が人とともにあるわけですよね。ただ見て、うーんとなるだけじゃなくて。いろいろ考えると、斉藤先生の絵は、絵が一緒に生きてくれるための絵という気がしました。ただ見て、わっとなるという、見られるためだけじゃなくて、絵が一緒に生きているという。入口の4枚は、絵がわたしたちのいるための、そのための場所というのをお考えになったのかなと。
斉藤:うーん…
吉田:わたしの言葉で言えば、そうかなと感じまして。
斉藤:これを今回展示したのですけど、元々は掛軸を考える韓国・ドイツとの交流展のために作った作品ではあったので、現代的な掛軸の活かし方なり、そこで共有していた空間や時間を私の時間、空間で表すとこういう風になりますというものです。
吉田:あの、さえぎってよいですか?先生のお話を途中でさえぎって申しわけないのですが、民俗学とおっしゃったので、民俗学のことを伺いたいのですが。さっき、文楽と聞き違えして、義太夫なんて言ってしまったのですけど、ご先祖の方に俳人の方がいらして、またご本もとても好きだったんだと思って。それに今回の題の内にある「森の肤」という難しくて地味な文字を読めなくて、漢和辞典で調べたので。そういう文字とか文学、それから言葉などにも敏感な方だと思ったので…民俗学というと、文学が専門ですのでまず初めに折口信夫とか文学系として思うんですけど、詳しくお伺いしてもいいですか。
斉藤:民俗学の方にも関心はあったのですが、どちらかと言うと部族の方ですね。
吉田:あっ、2つありますね、民族学。そっちの方ですか。アーリア民族という時の民族
斉藤:そっちの方に…。人間自体がどういったものかという方に興味があって。
吉田:人類学に繋がるようなところですよね。
斉藤:繋がる所ですよね。アフリカに行ってサルの研究とかもしたいなというのはあったんですが、京大は入れないしなと諦めたというか…。そういった方への興味も無いわけではないんですけれども。
吉田:わたしの勝手な思い込みで、民ゾク学のゾクは世俗の「俗」、俗っぽいの「俗」の方だと思っていて、自然の中にただものではない何か気配を感じるとか…。平塚で生まれて、平塚でお育ちになっていて、近くにこういう描く樹とか森があることが、先生の絵に関わっていると思いますし、そういう自然があればわざわざ海外に行く必要もないなと思いますので。高麗山というのはどういう山ですか?丘ですか?
斉藤:160m位の山ですね。山は山で、でも山としてはそんなに高くなくて、上から下まで20分30分位であれば行けてしまう所。
吉田:平塚だと、海も川も近い場所ですが、その山が先生の場所と言うか?
斉藤:民族学じゃないですけど、僕以外の場所の記憶が端的に表れている一つの象徴として捉えているような所がある。実際、子どものころからよく化石を掘りに行ったり、遠足に行ったり、歩いて20分位で行けるので僕の遊び場でもあったのですよね。高麗山という名前の通り、朝鮮の高句麗から高麗の人達が埼玉あたりまで移り住んでいって、縄文時代から見ると江戸の周りよりは、地面があって…というような場所で縄文海進期の頃、のちの江戸周辺は海の中だった。相模湾に初めて上陸するような所とかで…
吉田:地形的には、ほんとうにそういった方たちが住みつくような場所ですね。
斉藤:そういった人たちが住んでいた場所でもあったり、自分の御爺さんの大正舎麗山と言うのも、高麗山から取っているんですけど、麗しい山と言う意味で。書家の祖父と結婚した祖母も高麗山の裏側からお嫁に来ていたりとか、自分を形成しているものがそっちとすごく絡んでいるんですよね。単に象徴的に山というものを考えているわけではなくて、自分の記憶と絡みついたもの。
吉田:トポスと言うような場所なんですね。
斉藤:そうですね。
吉田:民族学ということで、例えば柳田国男の『遠野』の「でんでら野」というところが出てきますよね。それは大体、里山なんですよね。すごく高い山ではなくて、村の近くにもうちょっと高い場所があって、そこに亡くなった人や祖先がいる場所であり、その時間であり、それは決して遠い場所ではないというような…。ひょっとしたら、里山的な場所かなというふうに勝手に思っていたのですが…
斉藤:里山と言えばそうも言えなくもないのですけれども、ある意味、里山って人間が管理している地なんですよね。
吉田:そうですね。
斉藤:そうかと言うと、多分、大分少なくなりましたが、相模湾というか温暖性の樹木林が割と残っている。結構、昔とそのままの樹木林が残っているような山です。
吉田:いわゆる、原生林というとイメージは違うけども、そんなに人間が手を入れて植林しているわけではないと言う。
斉藤:そうですね。管理している所では無いので、逆に枯れてきちゃったりといろいろなことも起こっているんですけども、ある意味そういう意味で言うと、里山的な人間が関わって作り上げてきた自然ではない、人間が容易に素の自然に触れられることが出来る場所。
吉田:人間以外の時間も宿っている場所というか…
斉藤:山が山である場所。そういうのが歩いて20分位で行ける場所にあるという。ある意味、田舎というか…。
吉田:すごくうらやましいです。ずっとそこに住んで、育って、ご先祖様もそこに育っていて、こういう世界に出会っていらしゃることが。わたしにとっては楽しい、とても興味深いお話を伺って、わたしは打合せの時に次いで、さらに幸福な時間を今日は頂けました。
2012年度、斉藤典彦先生の個展「山水を憶う」という展覧会を7月に日本橋髙島屋美術画廊をなさった時のパンフレットに書いてある文章がすごく素敵で、わたしは「これは詩だ」と思って、ぜひそれを最後に読んでいただきたく存じます。そろそろ終わりが近いと思いますので、よろしくお願い致します。
斉藤:読むには長くないですか?
吉田:大丈夫です。夏は夜が長いので。
斉藤:「山水なるもの」
単に刺激的で視覚的なものが与えてくれるものよりも、更に大きな力を与えてくれる絵を描きたいと思う。全身が包まれるような、肌を通して感じるような、そういうものを。
直線的な時間ではなく、途切れなく循環する時間、繰り返す営み。
一回見ただけで描けるようなものではなく、繰り返し感じることで積み重ねられた記憶のような、そういうものを描きたい。現実の時間や自我の実在を描くのではなく、全てをあるがままに受け入れることで見えてくる、もっと大きなものを描きたいと思う。
「美しい」花はあるが、花の美しさはない。分析するのではなく、まるごと飲み込み、飲み込んで感じるもの、そのようなものへの接し方を引き継いでいきたいとおもう。
モニターに映るものがスイッチを切ってしまえば、この世に存在しないものの如く、その姿はかき消える。しかし、目の前にあるものが目を瞑ることでなくなってしまうわけではない。都市で語られる歴史とは異なった時間に寄り添うことにより、目を瞑ってもものはそこに在るものとなる。
水をたっぷり引いた画面に絵の具を垂らす。絵の具が、岩絵の具の一粒一粒が拡がるさまはそれだけで大きな世界の一つの謂と私には思える。この世界を自分の指を通して、この古くさい顔料、膠、基底材がもたらす触覚的な記憶に置き換えること、ひいては線や色の抽象性に置き換えること。それは視覚的なものが一瞬にしてもたらす効果に比べれば、描く者にとっても、視るものにとっても、遥かに辛抱を必要とする。しかし、欲望を満たしていくことより、欲望を切り捨てていくこと、それがこの限られた世界に真に自由な空間を生み出すための唯一の手段になると思う。