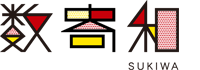楮皮むき・表皮(黒皮)けずり
2010年3月6日(土)・7日(日)の二日間、ギャラリーSindにて楮皮むき・表皮(黒皮)けずりを行いました。
蒸した楮の皮(黒皮)を幹から剥ぎ取り、内皮(白皮)だけにする作業です。この内皮が紙の原料になります。
指導してくださったのは、Richard Flavin(リチャード フレイビン)さん。
版画を学ぶためにアメリカから来日し、手漉きの紙に魅了され、自ら紙漉きをはじめて20年!今は埼玉県の越生にアトリエ兼住まいがあります。今回の楮も埼玉県の小川町で刈り、蒸した楮を使用しました。
原材料である楮を育て、そして紙を漉き、その紙をつかって作品をつくります。紙とまるごと関わることが彼の創作活動です。
少しですが、楮皮むき・表皮(黒皮)けずりをご紹介したいと思います。
 |
蒸した楮を水につけて置き、皮を剥ぎやすくしておきます。
本当は、蒸し終わってすぐ温かいうちに剥くと作業が早いとのこと。
今回のために、リチャードさんが水につけて置いてくれました。 |
 |
リチャードさんのお手本。
楮の皮むきです。
芯と皮とのあいだは糖分がありベタベタしています。
このベタベタがあることで、つるっと芯からむけ易くなります。
注意しなければならないのは、皮は90度にむくこと。
直角でないと、皮が裂けてしまい、上手く黒皮けずりができません。 |
 |
黄色いのが皮をむいた芯だけの部分。
これは腐り易いので、乾燥させて薪に使うそうです。 |
 |
むいた楮の皮。
中の内皮だけが紙の原料になります。
外の黒皮を漉きこめばチリ(黒皮)入りの紙が出来ます。 |
 |
いよいよ本番!
楮皮むきです。木の板に皮を平にし、ヘラで一番外側の黒皮を剥ぎ取ります。これがなかなかの重労働。
上手くぺりぺりとむける皮はいいですが、細く裂けてしまうこともあるので、そうなるとヘラで何回も剥ぎとらなくてはなりません。 |
 |
リチャードさんのお手本。
さすがに慣れていて、早い・きれいです。
黒皮が残っていると、白い紙にはなりません。 |
 |
やっとここまで出来ました!
この内皮を干し乾燥させ、また蒸してから、叩きほぐします。
そしてやっと紙が漉けるようになるのです…。
自ら作業をすると、私たちが使っている紙の貴重さに気付きます。
また、手すきの紙は本当に手間隙がかかり、職人の丁寧な作業によって作り出されている素晴らしいものなのだと感じることが出来ました。 |
 |
干して乾燥させている、楮の内皮。
きれいです。
叩きほぐすと白くなります。 |
紙作り
楮の皮むきの会に引き続き、3月21日(土)・22日(日)にギャラリーsindにて紙すきの会が行われました!
前回干して帰った白皮を、リチャードさんがソーダ灰で煮ておいてくれました。その皮を叩いて、
繊維を細かくするところから、ワークショップの始まりです。




 |
みんな手取り足取り、リチャードさんに教わりながら、紙をすいていきました。
紙床がどんどん厚くなっていきます。
穏やかな快晴の中、紙料をすくう、チャポチャポと良い音が響き、心と体に澄み渡ります。
こんなにたくさんの紙がすけました!
|
 |
すいた紙を重ねた紙床を、プレス機にかけて圧搾(脱水)します。
量が多いので、大体一晩はこのままにしておくとのこと。
弱い圧力で、ゆっくりと水を抜きます。 |
 |
翌日、数寄和スタッフがシンドさんを訪ねると、板に紙が干されていました。
リチャードに教わって紙床から紙をはがして干していきます。 |


 |
専用の刷毛で、やさしく紙を一枚づつ紙床からはがしていきます。
(紙と紙がくっつかづにはがれるのは、トロロアオイのおかげなのです)
それを板へ、空気が入らないように刷毛で撫でつけていきます。
板は、アクがでないように、古いものでなくてはいけません。
風が強くてたいへんでしたがなんとか板張りができました! |
 |
天気が良く、2時間ほどで乾燥しました。
板からペリペリと小気味良くはがれます。
ほんのり生成り色の楮紙が出来上がりました。 |
まだまだ奥深い和紙作りの世界。
ぜひみなさん数寄和に遊びにきて、その魅力に触れてみてください。