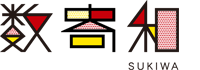2024年10月24日から11月3日、室井佳世展を開催いたしました。
多くの方にご来場いただき、ありがとうございました。
室井先生の展覧会作品を様々な視点から楽しんでいただくために、
詩人の藤原安紀子さん、画家の蒜山目賀田(ひるぜん めがた)さん、ライターの大瀬友美さんに鑑賞文をいただきました。
________________________
森の文節 –––室井佳世展によせて
藤原安紀子
水底をトンと蹴って。わたしたちの縁鳥(ふちどり)へおとずれる色。
深緑の里山の中腹からながめると、千種川は輪郭のない色について考えている。隔てるものがなければあるともないともいえない色は、そとに包まれて生りうちに湧きいでて滲んでいた。せいしもなく流れている。
翼のない縁鳥(ふちどり)とこわれていないものをそっと抱きしめる。千種はうたいながら幽かな漣を、線にも輪郭にもしないで住まわせている。
森はしずかにまじわりはじめていた。
岸からひき連れてきた待宵草を若い木馬が食べたいという。いたずらに髪に挿した一輪がとめどなく繁殖し、静物たちは甘いミントティーの湯気の奥で揺れたまま、クロスにこぼれた水滴の笑い声にほころぶ。
死角はふくらみつづけ、あふれていく再生。
色を有る。氷花が黙してひらき、またたく間に実をむすぶ。かたい真果を神秘のように捥いで、形質から遠くへ離散させていく。縁鳥(ふちどり)は倍音のハミングをくりかえし、くる日もくる日もしゅうれんしている。
________________________
室井佳世 展 蒜山目賀田(ひるぜん めがた)
展示室にはいるなり目に、暖色のはなばなしさがうれしい。赤や黄色の絵の具は、紙のうえで、形や柄(模様)、あるいは光になりながら踊り、かつ、身をよじり、形や柄、光から抜け出そうとする。けれども、やかましいほどではない。わきまえられた賑やかさにとどまる引き締まり方に品がある。目の前のものは厳しくあくまで平面にい続けている。絵の描かれた物体が、たしかにある、という力強さ。なんていうかその、すっきり真面目なんである。身が詰まっている感じがする。パネルなんだから持てばそれほどの重さはないだろうのに、実際よりよほど重い予感がたつ。落とせばガラスのようにがりんと割れる緊密さがある。
無邪気さを装って描いたと見ることもできる。反対に、つい無邪気さがはみだしてしまった絵とも見える。しかしいずれにせよ、根本にはなにか、生硬な、一本気なものがある。見ないうちにずいぶんおとなびた子供が、久々会う叔父や叔母を前にして、それまでそんなことなかったのに、こわごわ、ぎこちなく敬語を使っていじらしい。そんな真面目さだった。
作家のいろ、をみるために、表面の物質性に目が慣れて飽きるまでひとまず眺めきる。そのむこうにどんな息遣いがあるか、じっと凝らしていると、闊達さ、という言葉が出た。ひと目では、すっとはなばなしい色が目立った絵の具が、かつて画面上で過ごした時間に、視線がたどり着く。麻紙の繊維に沈みながらとなりあう色にとろりとかぶさって、半透明になった。上流の澄んだ瀞に沈んで崩れずにいる、熟れて落ちた果実を見下ろしている。
________________________
室井展レビュー 大瀬友美
室井佳世の作品には花のある暮らしが描かれる。花が生けられ、家具や食器にも植物模様が多用されている。この部屋を調えた住民の息遣いが細部に込もっているようだ。しかし住民の姿は描かれないため、その存在を考えた途端に不在を認識せざるを得ない。古い壁画のようなマチエールと相まってポンペイを思い出した。もういない人々の暮らしを生々しく伝えるタイムカプセルのような街である。
他方で人物を描く作品の場合には、背景に草木や街並みが装飾的に描かれて抽象的な空間が出現する。そのなかにたたずむ少女の表情は寡黙で、幼くむくれているようにも見えるがそれ以上にマリア像や観音像のような厳かさを放っている。
展覧会のなかで異色なのは山とその麓を流れる川を描いた一枚だ。他の絵が現在と過去、存在と不在、夢と現のあいだをたゆたうような曖昧な雰囲気を持っているのに対し、この絵だけははっきりと現実的である。それもそのはずで、これは室井が実家の家仕舞いをした日に見た風景だという。「もう二度と見ることはないだろう」というこの故郷もまた、次第に現実から遠ざかって記憶のなかの存在になってゆくのだろう。
________________________
出展作品