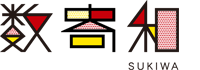蒜山目賀田
今回のSeijiMurakami展、この作家は初見だったが、ダイレクトメール掲載作の印象を勝手に膨らませたうえで会場にむかったら困った。ほとんどの作品が、予想していたトーンとは違ったからだ。もっと重たく、硬い雰囲気の絵画を想定していた。おまけに、展示作品ひとつひとつのスタイルも多種多様で、「どんな展覧会だったか」をまとめるのも難しい。早とちりが外れただけでこんな言われ方をされるのはいい迷惑だろうが。
強いて共通点を言えば、すべての作品は、数種類の紙を組み合わせてつくられている。多くは和紙である。切った紙や破った紙を組み合わせたり、裂いた部分をねじって、こよりにしてみたり、種々の工作をしている。
子供のころ、シールを貼って遊んだあとに残る、枠組みだけになったシール台紙の、その枠組みも結局はシールなので、そいつもどこかに貼りつけたくなったものだ。そんなことを思い出した。これといって目指すものはないが、素材の呼び声に応じ、つい体が誘われてしまうという営為。図画工作というんじゃなく、図画工作的、とでもいおうか。そういう作品群であるようにはみえた。あたたかな部屋、編み物のまねごとで過ごす子供の姿が幻視される。
ちょっと見ると絵っぽい。けれどもよく見ると、ぼく個人の基準としての「絵画を組み立てる際に意識するだろうポイント」ではつくられていないように思えた。それは例えば、点や線や面という単位を基本にして組み立てているだとか、ひとつひとつの形や色合いや素材の質感への強迫的な執着だとか、画面上にちりばめられた複数の形たちの影響関係への用心の程度のことだが、もちろん、こんなのはただ自分勝手なシロモノである。独断である。で、だけどもともかく、私自身の感想として、この展覧会にあっては、そういう神経はあまり反応しなかった。
とはいえ、「織る」とか「こよる」とか、「穴をあける」とか「重ねる」とか、まあなんでもいいのだけど、ひとつの行為に過剰に注力することであらわれてくる「しつこさの総量」でぶん殴ってくるようなタイプでもないように感じた。要するに結局のところ、いまの自分には、感想文を書くことが難しく思われたのだ。しかしこれはネガティブな意見ではない。既知の感覚では対処できないなにごとかが秘められている可能性を示唆する結果である。
鑑賞体験の楽しみはいくつもある。造形的な特徴に目を遊ばせたり、描かれている世界に思いを馳せたり、ときに別のなにごとかを連想したり、さまざまだが、「この作家はなにに目をつけている人なんだろう」と推理する楽しみもたまらない。個展となるとなおさらだ。
ただし、推理するためには、その作家の作品を、まずはじゅうぶんに体験しなければならない。データ不足じゃ話にならない。だから、初見の作家の場合は、鑑賞体験の質×量の積がまだ少ないのでうまいこと飲み込めない場合がままある。何年かかけて、何度もじっくり観察して、ようやく自分なりに腑に落ちる、というケースはまったく珍しくない。